INFORMATION
診療について
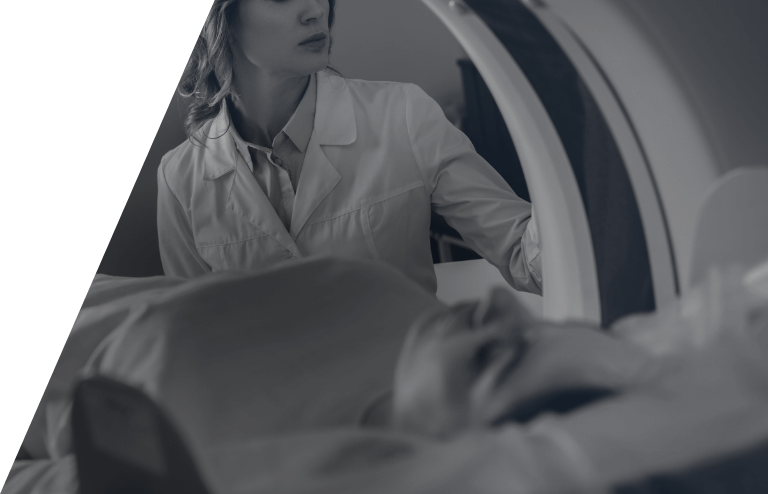
診療案内
放射線科では、単純X線撮影、CT、MRI、超音波、核医学、血管造影など、さまざまな画像診断装置を用いて全身の病変を評価しています。
当科では現在、多列検出器CT(MDCT)3台、3テスラMRI 2台、1.5テスラMRI 1台、PET-CT装置、SPECT装置などを備え、各診療科と緊密に連携しながら、疾患や臨床状況に応じた最適な検査法と撮像条件の選択に努めています。
CT、MRI、核医学検査については、放射線科専門医が画像を読影し、可能な限り迅速に(原則として翌診療日までに)病院情報システムを通じて診療科へ報告しています。
また、IVR(画像下治療)や放射線治療といった低侵襲の治療においては、放射線科医、診療放射線技師、看護師が一体となって対応し、患者さん一人ひとりの病状に応じた治療計画を立案・実施しています。安全かつ効果的な治療を提供することを目指し、常に丁寧で寄り添った医療を心がけています。
代表的な放射線科の医療機器
-
CTComputed Tomography

X線を利用して体内の断層像を構築する画像診断法です。高い空間分解能と撮像速度を備えており、全身のあらゆる疾患の評価などに優れています。造影剤を併用することで、血管、腫瘍、炎症の描出にも有用です。近年では、Dual-energy CT や 4D-CT angiography などの高度な画像解析も臨床に応用されています。
当院では、320列の多列検出器CTを含むハイエンド機種のDual-energy CT 3台が稼働しており、幅広い臨床ニーズに対応しています。 -
MRIMagnetic Resonance Imaging

高磁場とラジオ波パルスを用いて、水素原子核から得られる信号を収集・再構成する非侵襲的な画像モダリティです。高い軟部組織コントラストと多彩な撮像法(T1/T2強調像、拡散強調像、灌流画像、MR angiography、造影ダイナミック検査など)により、脳神経系、頭頸部、乳腺、縦隔、腹部、骨盤臓器、骨・関節領域など、あらゆる部位の精密評価が可能です。造影剤を用いずとも高精度な情報が得られる点も大きな利点です。
当院では、3T装置2台、1.5T装置1台のMRIが稼働しており、先進的な画像診断を支えています。 -
核医学Nuclear Medicine
放射性同位元素(RI)で標識したトレーサーを体内に投与し、その分布や代謝をガンマカメラやPETで可視化する手法です。生体機能を画像として可視化できる唯一のモダリティであり、骨シンチグラフィ、心筋SPECT、脳血流SPECT、FDG-PETによる腫瘍代謝評価などが代表例です。
CTとのハイブリッド装置(SPECT/CT、PET/CT)が標準化されており、形態情報と機能情報の統合的評価が可能です。特にFDG-PETはがん診療に不可欠であり、また、アルツハイマー型認知症の診断に用いるアミロイドPETも実施しています。 -
超音波US:Ultrasound
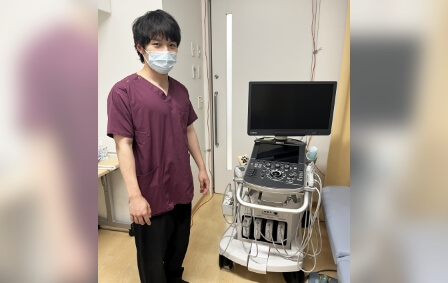
高周波音波を用いて体内構造をリアルタイムに描出する非侵襲的かつ即応性の高いモダリティです。被ばくがなく、繰り返し使用可能であることから、腹部、乳腺、表在臓器、心臓、血管など多くの領域で汎用されています。ドプラ法による血流評価も可能であり、診断精度を高める補助的手段として有用です。一方で手技依存性があるため、熟練した技術と経験が求められます。ベッドサイドでの柔軟な運用が最大の利点であり、急性期医療においても重要な役割を果たしています。
-
血管造影検査・IVRangiography・interventional radiology:画像下治療
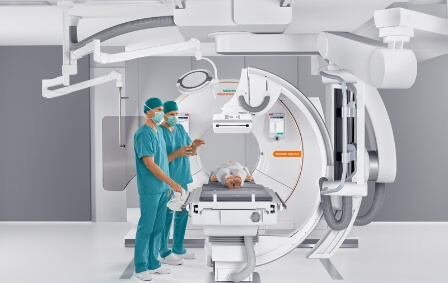
血管造影検査はカテーテルを血管内に挿入し、造影剤を使用して血管の状態を調べる検査です。現在は血管造影カテーテルを使用した血管内治療(IVR)が普及しています。脳、心臓を除くほぼすべての領域のIVRを行っています。体への負担が小さいことがIVRの最も大きな利点です。放射線部には2台のIVR-CT装置、2台のバイプレーン血管造影装置を導入しています。また、手術部にも2台の血管造影装置(Hybrid OR)が導入されています。
-
放射線治療Radiation Therapy
最新の治療機器と専門スタッフによる高度な放射線治療を提供しています。がんの根治を目指した治療から、症状の緩和を目的とした治療まで、患者さん一人ひとりに最適な医療を届けることを目指しています。
当院では現在、以下の治療装置を稼働させています。高精度リニアック[放射線治療装置]2台
強度変調放射線治療(IMRT/VMAT)や定位放射線治療(SRT/SBRT)などの高精度な照射に対応しています。
小線源治療装置 1台
婦人科悪性腫瘍などに対して、体内から放射線を照射する治療を行っています。
治療計画用CT装置 1台
正確な治療計画を立案するために、高精度な画像データを取得しています。
放射線治療計画システム
高度な線量分布の設計が可能なシステムを用い、がん病変に的確に線量を集中させる治療計画を作成しています。
これらの機器を用いることで、肺や肝臓、前立腺、脳腫瘍など、さまざまな部位のがんに対する精密な照射が可能となっています。また、呼吸性移動を考慮した呼吸同期照射にも対応し、正常な組織への影響を最小限に抑えた安全な治療を行っています。
疾患について
放射線科が対象とする疾患は非常に広範囲にわたり、ほぼ全身の臓器・組織に関わる疾患をカバーしています。
以下に、主要な疾患カテゴリと具体例を挙げてご説明します。
-
画像診断
Diagnostic Imaging画像診断は、CT、MRI、超音波、核医学(PET・SPECTなど)といった医療画像機器を用いて、身体の内部を可視化し、病気の早期発見や状態の把握、治療方針の決定に役立てる診療分野です。
-
1.脳、脊髄の疾患
・脳腫瘍(神経膠腫、髄膜腫、転移性脳腫瘍など)
・脳血管障害(脳梗塞、脳出血、動脈瘤、脳動静脈奇形など)
・脱髄疾患(多発性硬化症、視神経脊髄炎などなど)
・感染症・炎症性疾患(脳炎、髄膜炎、膿瘍、自己免疫性脳症) -
2.頭頸部の疾患
・副鼻腔炎、耳疾患
・頭頸部癌(咽頭癌、喉頭癌、甲状腺癌など)
・唾液腺腫瘍、リンパ節腫大 -
3.胸部の疾患
・肺癌
・肺炎、間質性肺疾患
・縦隔腫瘍
・大動脈瘤・解離、心疾患 -
4.腹部・骨盤の疾患
・肝胆膵疾患(肝癌、胆道癌、膵癌、肝硬変など)
・腎・副腎・膀胱の疾患
・消化管疾患(腸閉塞、腸炎、消化管出血、癌など)
・婦人科疾患(子宮頸癌、子宮体癌、卵巣腫瘍) -
5.骨・関節疾患
・骨腫瘍(良性・悪性)
・変形性関節症、関節リウマチ
・骨折、感染、壊死 -
6.小児疾患
・小児特有の腫瘍(神経芽腫、腎芽腫など)
・発達異常、先天奇形
・感染症や外傷 -
7.全身性疾患・血液疾患
・悪性リンパ腫、多発性骨髄腫
・膠原病関連の臓器障害
・代謝疾患
-
-
IVR
Interventional Radiology:画像下治療対象疾患は多岐にわたり、出血の制御、腫瘍の治療、狭窄や閉塞の解除、膿瘍や体液の排出など、低侵襲で体に優しい治療を可能にしています。
-
1.出血に対するIVR(止血術)
・消化管出血(潰瘍、腫瘍、憩室など)
・外傷による臓器出血(脾臓、腎臓、骨盤骨折など)
・産科的出血(産後出血、癒着胎盤など)
・喀血(気管支動脈塞栓術:BAE) -
2.腫瘍に対するIVR(治療的塞栓・化学療法)
・肝細胞癌(肝動脈化学塞栓術:TACE、薬剤溶出ビーズ:DEB-TACE)
・頭頸部癌の動注化学療法
・転移性肝腫瘍(化学療法や塞栓術)
・腎癌、膀胱癌、子宮癌、骨盤内腫瘍などへの動注療法や塞栓術
・子宮筋腫(子宮動脈塞栓術:UAE) -
3.狭窄や閉塞に対するIVR
・血管などの狭窄に対するステント挿入
・門脈圧亢進症に対するシャント作成(TIPS) -
4.膿瘍などのドレナージ、各領域の生検
・肝膿瘍、腹腔膿瘍、骨盤内膿瘍などへの穿刺・ドレナージ、各領域の腫瘍のCTガイド下生検など
-
-
放射線治療
Radiation Therapy放射線治療は、悪性腫瘍(がん)に対する局所治療の一つであり、近年では一部の良性疾患や機能的疾患にも適用されています。
-
1.中枢神経系疾患
・脳腫瘍:神経膠腫、髄膜腫、転移性脳腫瘍、下垂体腺腫、聴神経腫瘍 など
・脊髄腫瘍:髄内腫瘍、髄外腫瘍、脊椎転移 など -
2.頭頸部腫瘍
・咽頭癌、口腔癌、喉頭癌
・唾液腺腫瘍
・甲状腺癌(再発例・遠隔転移例) -
3.胸部腫瘍
・肺癌(小細胞肺癌、非小細胞肺癌)
・食道癌
・乳癌(術後補助療法、局所再発) -
4.消化器系腫瘍
・肝細胞癌
・膵癌
・直腸癌(術前・術後照射)
・胆道癌 -
5.泌尿・生殖器系腫瘍
・前立腺癌(外照射、小線源療法)
・膀胱癌(膀胱温存を目的とした化学放射線療法)
・精巣腫瘍
・子宮頸癌(外照射+腔内照射)
・子宮体癌、卵巣癌(再発例) -
6.骨・軟部・皮膚腫瘍
・骨転移(疼痛緩和、病的骨折の予防)
・軟部肉腫
・皮膚癌、皮膚転移 -
7.血液悪性疾患
・悪性リンパ腫(限局病変に対する局所照射)
・多発性骨髄腫(骨病変による疼痛緩和)
・白血病(全身照射:造血幹細胞移植前処置など) -
8.緩和的放射線治療
・骨転移による疼痛の緩和
・脳転移に伴う症状の軽減
・出血、神経症状、嚥下障害などの症状緩和 -
9.良性疾患・機能的疾患
・ケロイド
・甲状腺眼症(眼球突出)
-
オプトアウトについて
臨床研究のうち、診療行為の妨げにならず、患者さんへの新たな侵襲や介入を伴わず、血液などの試料を用いずに診療情報(画像・診断結果など)を用いて行う「観察研究」においては、国の定める倫理指針により、すべての患者さんから個別に文書で同意をいただくことが必須ではない場合があります。しかしながら、そのような研究を行う際には、研究の目的や内容を患者さんに対して十分に公開・周知し、できる限り研究への不参加(オプトアウト)を選択できる機会を設けることが求められています。このような手続きを「オプトアウト方式」と呼びます。
オプトアウトを実施している
臨床研究について
当科で現在オプトアウト方式により実施している臨床研究は以下の通りです。
研究へのご協力を希望されない場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご連絡をいただいた場合、その方の診療情報は当該研究には使用いたしません。
- 肺癌発症リスクの高い肺線維症CT画像を検出する解析基盤およびAI作成
- 当院における下咽頭癌の長期治療成績と晩期有害事象の遡及的解析
- 「画像-病理対比検討に基づく高分解能CTによる病理組織学的UIP(Usual interstitial pneumonia)パターンの検出」に関する研究
- 乳癌診断におけるMRI 撮影標準化に向けた複数施設前向き研究
- 深層学習を用いた呼吸同期CT画像の解析結果が放射線治療計画に及ぼす影響についての後方視的臨床研究
- UltrafastダイナミックMRIにおける乳房病変の3Dデータ抽出とradiomics解析
- 当院における髄膜腫術後に対する放射線療法の治療成績と有害事象の遡及的解析
- UltrafastダイナミックMRIを用いた乳癌の診断能及び予後因子との関連に関する研究
- 乳巌予後因子のMRI画像所見の検討
- 膠原病患者への放射線治療の安全性評価
大学病院へのご案内
画像診断部門および画像ガイド下治療部門では、外来や病棟を持たず、すべての診療を各診療科からの依頼に基づいて行っています。CTやMRIなどの画像検査の品質管理と診断(読影)を担っており、各診療科との合同カンファレンスや研究活動を通じて、患者さんを中心とした診療体制の充実に努めています。診断装置としては、4台の多列検出器CT(MDCT)、1台の1.5テスラMRI、2台の3テスラMRI、1台のPET-CTが稼働しています。
放射線治療部門も病棟は持たず、各診療科の依頼により診療を行っていますが、外来は設置されており、外来での放射線治療も可能です。治療装置としては、2台の放射線治療装置(うち1台は高精度放射線治療に対応した装置)と、1台の小線源治療装置が稼働しています。受診希望の方は放射線治療の受診をご希望の方は、以下のURLをご確認のうえ、ご予約をお願いいたします。





